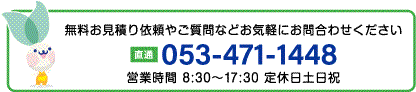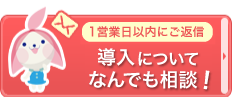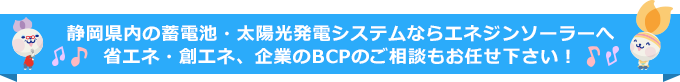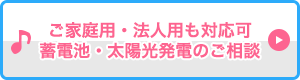省エネ・創エネ お役立ちコラム
災害対策
2018年11月20日災害対策
―いつか来る大地震に備えて知っておきたい― 避難所での生活について
今年は特に台風、地震により大きな被害が多かった年と感じている方が多いのではないでしょうか?
7月に発生した台風7号と梅雨前線等の影響により200人以上の死者が出てしまった『平成30年7月豪雨』をはじめ、大阪では震度6弱、北海道では震度7、それぞれ死者も発生してしまい、特に北海道は道内全て停電してしまう事態、いわゆるブラックアウトを起こしてしまいました。
そして当社本社がある浜松市でも台風24号により大規模停電が発生し多くの方が不便を強いられたことはまだ記憶に新しいところです。
今後、ご自身やご家族また身近な人たちがいつ未曽有の大災害に巻き込まれるかわかりません。
皆さんそれぞれ備えはされていると思いますが、災害発生後にまず逃げる先は「緊急避難場所」です。
皆さんはご自身の「緊急避難場所」はどこかご存知でしょうか?
【「緊急避難場所」と「避難所」の違い】
「緊急避難場所」
災害が発生したらまず逃げる場所です。台風、地震、津波など災害の種類ごとに予め指定されています。

「避難所」
災害により自宅が倒壊、滅失等した場合に一定の期間避難生活をする場所です。
具体的な施設としては、小中学校の体育館や公民館などの公共施設になります。

浜松市の緊急避難場所
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kiki/disaster/bousai/hinankoudoukeikaku/kinkyuu.html
※災害対策基本法の一部改正により「緊急避難場所」「避難所」をはっきり区別することになっています。
自宅にいられなくなった場合、避難所での生活が必要になります。しかしその実態は想像以上に過酷なものになります。
【避難所生活の実態】
避難所とされる学校や公民館などは居心地の良い生活空間ではないため寝泊まりするには適した場所ではありません。
■避難所は居住空間として不完全
1.避難所の環境
・床がたわむ、きしむ
・音が響く
・換気が良くない
2.就寝環境
・せき、いびき、子供の泣き声がうるさい
・知らない人と同じ空間で寝る
・床に寝るため体中が痛くなる、底冷えがする
・狭くて横になれない
3.トイレ
・数が足りないため長蛇の列ができる
・水が流せない
・周囲に気を使い夜中に行けない
4.防犯、トラブル
・お金、貴重品、食料が盗まれる
・いさかいが起こる
■食事・物資について
1.食事
栄養不足が懸念されます。
・同じものばかり
・温かいものが食べられない
・量が足りない
2.物資
被災者のニーズと、支援物資との間にはギャップがあります。
・薬がない
・衣類のサイズが合わない
・下着や生理用品、洗面用具がない
3.食料や物資の配布
災害の被害が広範囲に及ぶと支援がすべての避難所に行き渡らなくなり、避難所ごとに格差が出てしまう場合があります。
・物資の取り合いが起こる
・水ばかり届く
■入浴について
・体を拭いてしのぐしかない
・髪を洗えない
・お湯が足りない
《自衛隊の仮設風呂》
・1回につき最大で40人入浴可能
・深さがあるため介護が必要な人は注意
4)健康管理
・インフルエンザや風邪が蔓延しやすい
・エコノミークラス症候群を発生しやすい
【避難所では共助が重要】
〈災害時要援護者とは?〉
災害時に1人で避難あるいは避難所生活をするのが難しい人々のこと
・高齢者
・乳幼児
・妊婦
・難病患者
・介護者
・障害者
・日本語に不慣れな外国人
※自助とともに共助にも目を向け、避難者が災害時要援護者を支えられるかが重要。
【ペットはどうなるのか?】
〈各避難所の決めたルールに従う〉
ペットを避難所に受け入れると様々な問題が生じる可能性があるため、受け入れ可能な場合、そうでない場合がありますので避難所のルールに従わなければなりません。
《ペット受け入れへの意見の例》
・人命が最優先
・動物が苦手な方、またアレルギーの方がいる
・ペットを置き去りにできない…
・動物がいると癒される
・人も動物も同じ

《注意》
・受け入れが許可されても、飼い主は責任持って抜け毛や臭い、排泄物の処理などの衛生管理が必要
・ペットと一緒に入所できないといって無理に車中泊を続けるとエコノミークラス症候群に亡くなった方もいるようです。
【さいごに】
避難所での生活は実際に経験してみないと本当の過酷さや苦しさは知ることができないとは思いますが、事前に情報として持っておくことで最低限の心構えくらいはできるのではないかと思います。
まずは家族で避難所生活について話し合ってみてはいかがでしょうか?
そして身近な人、職場の人たちなど、一人でも多くの人たちに伝わることで一人でも多くの命が救われることに繋がれば幸いです。